「ゲームは好きだけど、勉強はあんまり好きじゃないな…」
そう思っている人は大勢いると思います。実際、自分もその一人ですから。
私も中学生や高校生の頃は、あまりにもゲームが好きで帰ったらずっとゲームばかりをしていたために、テストの成績が悲惨だったことが何度かありました。
新たな知識を得ることは楽しいことかもしれませんが、その過程が辛いために、躓いてしまう人も少なくありません。
その一方で、ゲームは目標に向かって歩んでいくその苦労さえも、楽しいプレイの一環と変えてしまうのです。だからこそ、我々ゲーマーはゲームをこよなく愛するのかもしれません。
「勉強もゲームのように楽しければなぁ…」なんて思ったことは一度だけではありませんでした。ゲーム大好き人間としては、「ゲームは好きだけど勉強はしたくない」という気持ちがやはりあるのです。
ですが、もしもゲームをしながら勉強も一緒にできたなら、最高だと思いませんか?
今回は、ゲームをしながら歴史を学ぶことができる、そんな魅力的な方法について紹介していきます。
目次
本当にゲームで勉強できるの?
学校で行われる教育は、主に生徒の学力を高める目的で行われているものです。ですが、そもそも「学力」とはいったいどのような意味なのでしょうか?
そもそも、学力とは?
学校教育法第30条2項には、教育において重視されるべき三つの要素が示されています。
- 知識・技能
- 思考力・判断力・表現力
- 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
これら三要素を各教科ごとにバランスよく育成していくことこそが、学校において行われている学習なのです。
そのため、学校内のテストや大学入試の際にも、生徒の学力を図る基準として、これら3要素を考慮した問題内容となっています。
参考文献:令和7年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告(文部科学省)
無論、これは学校教育での話ですが、この3要素自体は、学校教育に限らない他のあらゆる学びにおいても重要な要素であるはずです。それでは、こうした3要素をゲームで育成していくことが果たして可能なのでしょうか?
「知識・技能」の習得における効果
知識・技能というのはすなわち、「何を知っているのか」「何を行うことができるのか」ということです。数学では方程式の使い方を覚えることや、歴史においては人物の名前や業績を覚えることが例として挙げられるでしょうか。
とはいえ、そうした知識というのは普通に勉強してもなかなか覚えづらいものです。知識があっても、それを実際に使う機会のほうが少ないのですから、長期的な知識として身に付きづらいのです。
しかし、ゲームを用いた学習であれば、知識や技能を体験的・反復的に身につけることが可能なのです。
例えば、人類文明の歴史と発展テーマとしたシミュレーションゲーム『Civilization』では、プレイヤーが実在する国や人物を操作し、年代ごとの出来事を追体験することで、歴史的知識を自然な形で獲得することが可能です。
このように、ゲームプレイを通した実践的な知識というのは、長期的な記憶として定着しやすく、普通に勉強するよりも効率的な学習効果を生むことがあるのです。
「思考力・判断力・表現力」の育成における効果
多くのゲームでは、プレイ中に思考力や判断力を働かせる場面が設定されています。
「限られたアイテムでどうやってボスを倒すか?」
「目の前の謎解きギミックはどうすれば解くことができるか?」
こうした問題解決や戦略構築、状況判断を繰り返す構造は、どのようなジャンルにも少なからず存在しています。
プレイヤーは仮説を立てて実行し、結果を評価するという思考のプロセスを繰り返すことによって、ゲームを楽しみながら実践的な思考力・判断力を育成することができるのです。
また、『Minecraft』といった創作系のゲームであれば、プレイヤーは自分で建物や複雑な仕組みを構築し、他者に見せる・説明するという楽しみ方をするなかで、自身の豊かな表現力を養っていくことができるのです。
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の形成における効果
ゲームのなかには、複数人で協力することでクリアを目指すジャンルもあります。そうした他者との関わり合いのなかで、プレイヤーは互いに協力しながら問題を解決していくことが求められていきます。
たとえば、『Overwatch』や『APEX』といったチーム協力型オンライン対戦ゲームでは、他者と協力しながら問題解決を図る活動が求められていきます。
ここでは、役割分担、コミュニケーション、相互理解、柔軟性といった人間同士のスキルが不可欠であり、こうしたプレイ体験を通じて協働的な学びの土台となる力が養われるのです。
ゲームで勉強することのメリット
このように、ゲームでも普通の学習と同じくらいの効果を得ることができるということを説明してきました。
しかし、ゲームの教育効果というのものにいまだ半信半疑な方もおられるでしょう。そこで、これからはゲームを用いた学習ならではのメリットについて紹介していきます。
モチベーションが維持しやすい
学習の最も大きな課題の一つに、勉強をするモチベーションを維持することが難しいということが挙げられます。しかし、ゲームを用いた学習方法であれば、こうした問題も解決することができるのです。
ゲームには、プレイの結果を映し出すスコア、レベル、アイテムなどの明確な成果がすぐに視覚化される報酬設計があります。
これは、心理学でいうところの「即時フィードバック」による満足感をもたらし、プレイヤーが「次もやってみよう」と思える動機づけになるのです。
たとえば、英単語を覚えた数に応じてポイントが加算される英語学習アプリなどでは、「努力が可視化される」ことで学ぶこと自体が快感に変わっていくのです。こうした仕組みによって、勉強を続けるモチベーションを保っていくことができます。
様々な知識に触れるきっかけになる
何もゲームだけで全てが学べるわけではない、ということも伝えておかなければならないでしょう。結局は、今までの方法で勉強していかなければならない場面も少なくありません。
「それでは意味が無いじゃないか」と思う方もいらっしゃることでしょう。とはいえ、ゲームのなかで見聞きしたことを様々な興味関心のきっかけにすることには、一定の教育効果があるはずです。
ゲームにはしばしば、複数の学問分野が融合して描かれていることがあります。
たとえば中世を舞台としたRPGでは、時代背景(歴史学)、建築物や服装(美術史)、戦術や兵器(軍事学・工学)、通貨や経済(経済学)、登場人物の心理(心理学)など、複数の知識が自然に登場してくるのです。
ゲームで見聞きした事柄は、知識として受け取るだけでなく、「もっと知りたい」「自分で確かめたい」という内発的動機を生み出し、様々な学問への自発的な接触と探究のきっかけとなります。
学習を強制されたものではなく、自ら学びたいと思わせるという点で、ゲームというのは教育的に非常に価値が高いといえるでしょう。
歴史学習に効果的なゲームタイトル
今までゲームの教育効果について紹介してきましたが、何も全てのゲームが学力向上に効果があるわけではありません。ここでは、歴史を学ぶうえで効果的なゲームタイトルを紹介していきます。
Assassin’s Creed(アサシンクリード)シリーズ
ユービーアイソフトから発売されているアサシンクリードシリーズでは、古代ギリシア、古代エジプト、ルネサンス期イタリア、革命期フランスなど世界各地にある実在の街を舞台として物語が進んでいきます。
当時の建築物・服装・風景・地図を精密に再現した都市を自由に行動することができるため、その地の歴史や文化を視覚的に学ぶことができます。
Fate/Grand Order(フェイトグランドオーダー)

Fate/Grand Orderとは、世界各地あらゆる時代の歴史上の英雄たちを召喚し、サーヴァントとして従えることで、世界を脅かす危機に立ち向かっていくストーリーのアプリゲームです。
数多くの英雄・偉人たちが登場するのですが、どのキャラクターも史実をきちんと調べたうえで、その設定を忠実にデザインされており、元ネタに対する深いリスペクトを感じる作品となっています。
とはいえ、なかには本来男性であった英雄が女性として登場していたり(ゲーム内できちんと理由が説明されています)、物語のなかで独自にキャラ付けされている偉人もいます。
しかし、そうした気楽な要素もあるからこそ、教科書でただ見るよりも、歴史上の人物を身近に感じながら学ぶことができるのです。
このゲームをしていた学生当時は、ストリートに登場した偉人の名前が歴史の授業に出てくると「あのキャラクターだ!」と一人でテンションを上げていました。
ただ身近に感じるというだけで、普段の歴史の勉強にもより高いモチベーションをもって臨むことができるのです。
まとめ
- ゲームを用いた学習でも、学校教育の三要素すべてをバランスよく伸ばせる。
- 普通の勉強方法にはない、ゲームだけのメリットも。
- 学習に効果的なゲームタイトルを選ぶことが重要。
いかがでしょうか。
ゲームを活用した学習、歴史の勉強におけるゲームの有用性について少しでも興味を持っていただければ、この記事を書いて良かったと思えます。
ゲームは、歴史を「読む」のではなく「体験する」ツールとして非常に有効です。
もちろん、全てが歴史を学ぶのに効果的というわけではありませんが、うまく選ぶことができたなら、歴史を今までよりもいっそう楽しみながら理解していくことができるでしょう。
今までの常識にとらわれない新しい学びのカタチを、ゲームと一緒に見つけていきませんか?

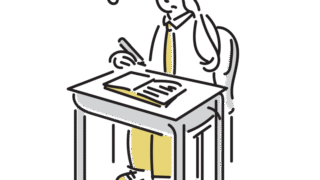


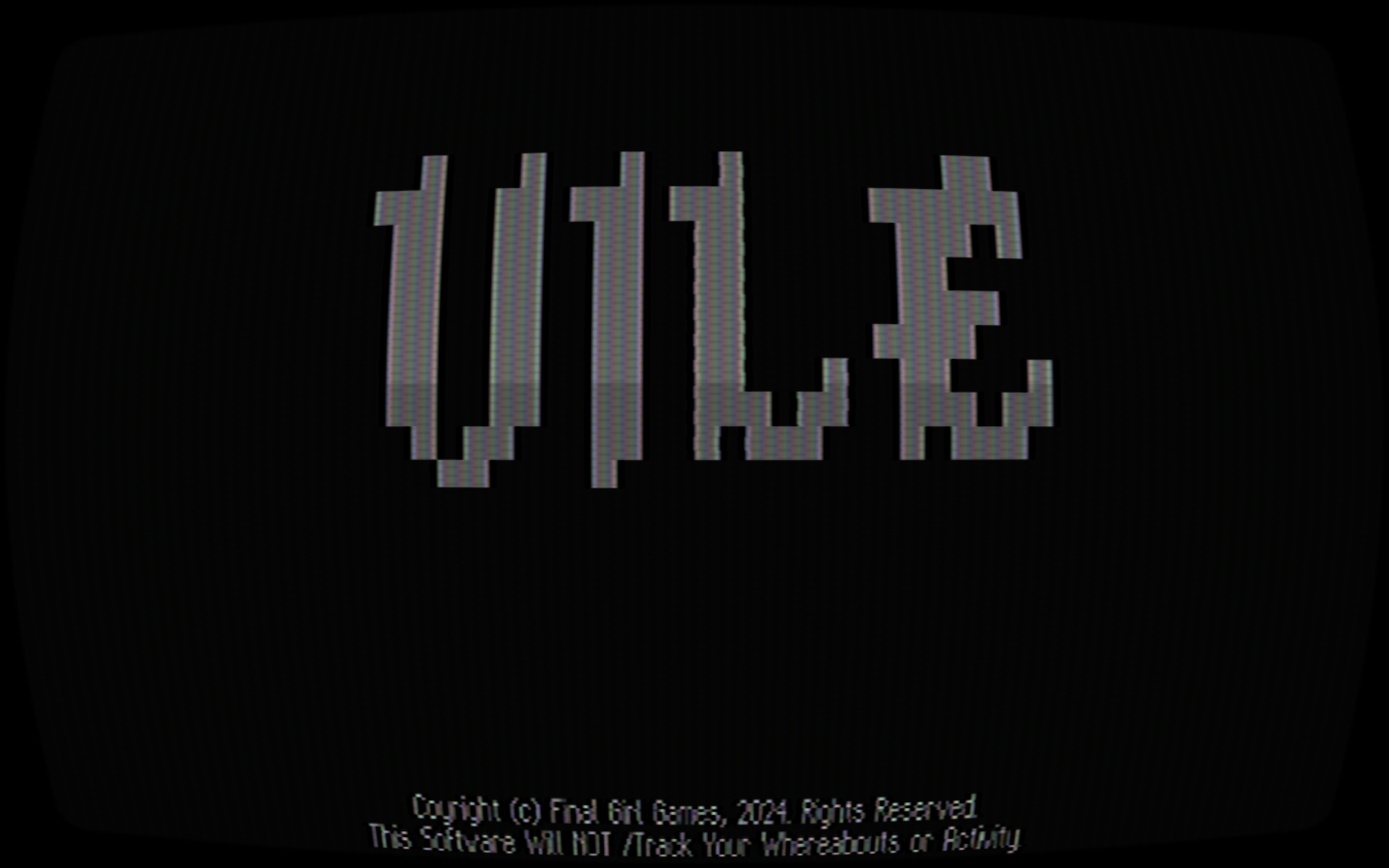
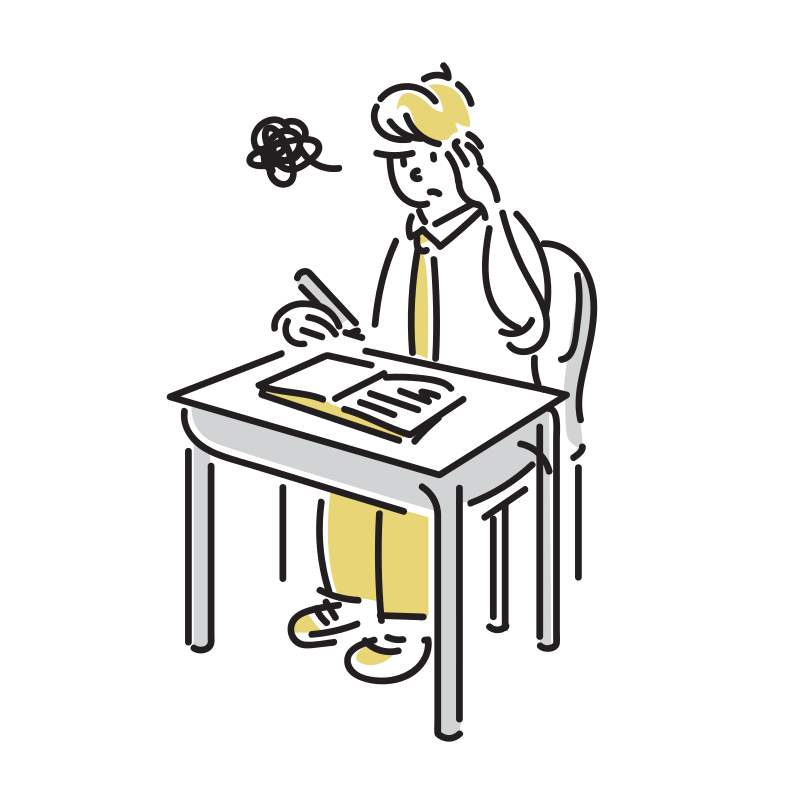


コメント